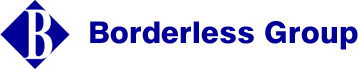2024年10月1日現在の日本の総人口は約1億2,380万1,000人。この内、日本国籍を有する日本人人口は約1億2,029万6,000人。総人口と日本国籍人口の差である約350万6,000人が永住または中期滞在の在日外国人の人口。在日外国人の人口比は2.8%だ。在日外国人には技能実習生・留学生・就労ビザ保持者・永住者・特別永住者など多様な在留資格の人が含まれる。
2024年の出生数は約72万1,000人で死亡数は約161万9,000人。差し引き約89万8千人が2024年年間での人口減少となる。出生数は2004年〜2015年の間、100〜110万人である意味安定していたが、2016年に100万人を割り込んでからは以下のように急速に減少している。
日本の出生数推移
2016 977,242人
2017 946,146人
2018 918,397人
2019 865,239人
2020 840,832人
2021 811,604人
2022 770,747人
2023 727,277人
そして2025年の1〜6月の出生数は毎月5〜6万人で推移しており、これを年間換算で65万人ぐらいになる数字だ。
日本の人口バランス
2024年10月1日現在の日本の人口構成は以下の通り。
年少人口(0~14歳):1,383万人(総人口の11.2%)
生産年齢人口(15~64歳):7,372万8千人(59.6%)
老年人口(65歳以上):3,624万3千人(29.3%)
————————————————————————
合計:1億2,380万1,000人
このあと数年で年少人口が急速に縮小して、そしてそれはじわじわと生産年齢人口の減少に拍車をかけてゆくことが容易に想像できる。
人口減少が社会保障政策に与える影響
日本は生産年齢人口である現役世代が老人人口の年金や保険を負担する賦課方式の社会保障制度を採っているので、現時点で約60%の人口が約30%の人口の生活費を賄っていることになる。現時点で現役世代二人で引退世代一人を支えているのだ。今でも公的年金や健康保険・介護保険などの社会保険料は増加の一途を辿っているが、今後もそれは続いて行くことが予想される。
また社会保障費はとっくに保険料だけでは足りなくなっているので、消費税などの税金からも支払われている。現在社会保障費の60%は社会保険料から、40%が国庫(税金)から支払われている状態だ。では年金受給者が十分な年金を受け取っているかというと決してそうではなく、こちらも物価上昇を加味した実質受給額は減少している。つまり社会保障は現役世代と引退世代の双方にとって満足のゆくものではない。
社会保障改革の可能性
一方で国を発展させるにはたくさんの若くて優秀な人材が必要であることは言うまでもない。年少人口を増やしてその教育に力を注ぐ必要があるのだ。そちらに支払うお金は投資のようなもので将来大きなリターンとなって返ってくる可能性がある。翻って社会保障費はとても投資になるとは言えず、ただただ消費になるばかりということは否めない。
そのどちらにも回せる潤沢な資金があれば良いのだが、そうでないのは明らかだろう。選択が必要になってくる、
国の将来を優先するのであれば社会保障にお金をかけるよりも若い世代を育む方に投資する方が良いのは明らかだ。だが年齢が高くなればなるほど、どうしても自分はもういないであろう数十年先の国の将来よりも自分の人生の安寧を優先してしまうのは人情。むろん自分たちが若い頃も社会保障費を負担してきたのでその望みには充分な正当性がある。
日本は民主主義の国であり、国が目指す方向性は投票を通じて決められる。人口バランスから年長者の思いは実現しやすくなり、その傾向はこの先どんどん強まってゆくだろう。
この流れを変えるにはどうしたら良いか?
多数決の民主主義に変わる政治体制。一人あるいは少数の意思で政策を動かせる独裁体制か、そこまでゆかなくてもある程度強い権力が集中している大統領制か。革命レベルの変化が必要になる。80年前に決められた憲法をわずかも変えられない日本人にとっては高い高いハードルである。